ARPはIPアドレスからMACアドレスを調べるプロトコルで、インターネット上で通信をする上で重要な役割を担っています。
今回は、ARPについて、初心者にもわかりやすく解説していきます。
ARPとは?

ARPとは、「Address ResolutionProtocol」の略称で、IPアドレスからそのコンピュータのMACアドレスを取得するためのプロトコルのことです。
そもそもですが、インターネット上で通信をしたい場合、IPアドレスとMACアドレスの2つの情報が必要です。IPアドレスはOSI参照モデルのネットワーク層で、PCがある場所を表す”住所”、MACアドレスはOSI参照モデルのデータリンク層で、PC一台につき一つ割り当てられた”名前”のようなものです。
だからこそ、IPアドレスとMACアドレス両方がわかって初めて「このPCがここにある」ということがわかります。
ちなみに、ARPはIPv4で使われるプロトコルですが、IPv6で使われるのはNDPと呼ばれる近隣探索プロトコルでARPの機能が提供されています。
ARPの仕組み、処理の流れは?
ARPの仕組み、処理の流れはいたってシンプルです。
①ARPリクエスト
まず、宛先MACアドレスを知りたいPCが、「このIPアドレスのPCのMACアドレスは何?」というARPリクエストを送ります。その際使われる通信がブロードキャストで、同じネットワーク内のすべてのPCにこのARPリクエストが送られます。
②ARPリプライ
次に、ARPリクエストへの回答として返されるのが、ARPリプライです。ARPリクエストを受け取ったPCは、自分のIPアドレスでない場合は応答せずそのまま破棄しますが、自分のIPアドレスと一致している場合、自分のMACアドレスをARPリプライとして返します。この際はリクエスト元にだけ届けばいいので、ユニキャスト通信が使用されます。
③ARPキャッシュ
一度①②のやり取りが行われた際、そのIPアドレスとMACアドレスは、ARPテーブルに一定時間保存されます。これをARPキャッシュと言います。その期間内に再度同じ宛先に送る場合は、わざわざARPを行わなくてもキャッシュを参照できるため、効率的です。
おまけー実際にARPを確認する方法
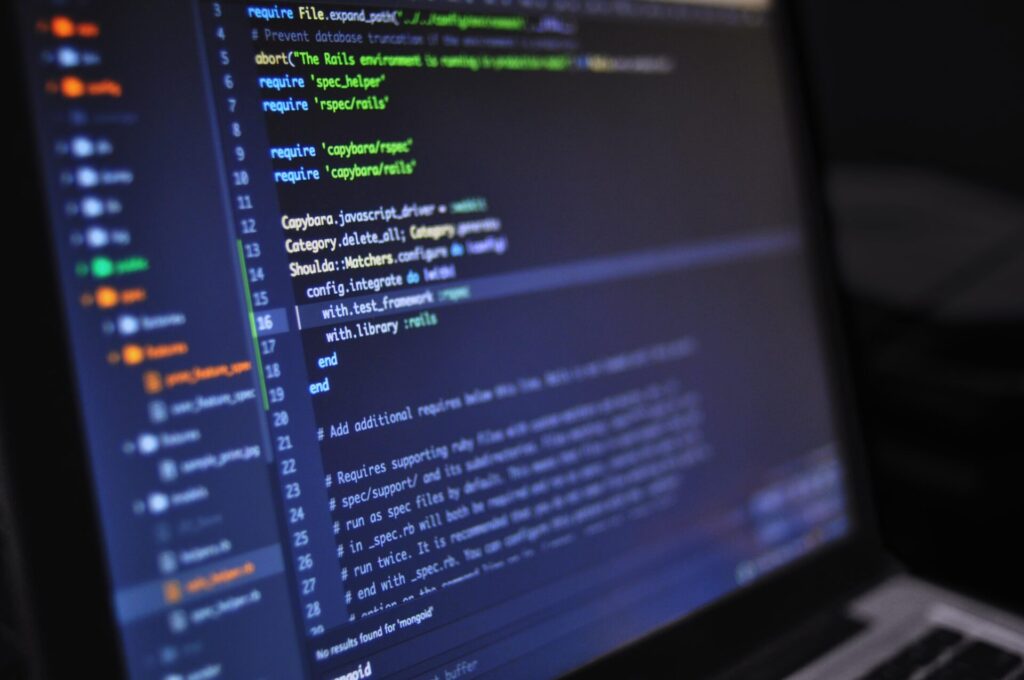
実際にパソコンでコマンドを打つと、ARPテーブルを確認することができます。
手順は簡単で、①「cmd」を打ってコマンドプロンプトを起動する②「arp-a」を打つと、ARPテーブルが表示されます。それを見ると、どのIPアドレスにどのMACアドレスが対応しているのかを確認することができます。
こういった通信の仕組みは文章で説明されてもあまり実感がわかないので、実際にコマンドを叩いてみてみるのがオススメです。
おわりに
いかがだったでしょうか。仕組みとしては単純ですが、このARPは通信をする上で欠かせないプロトコルなので、しっかり仕組みを押さえておきましょう。



コメント